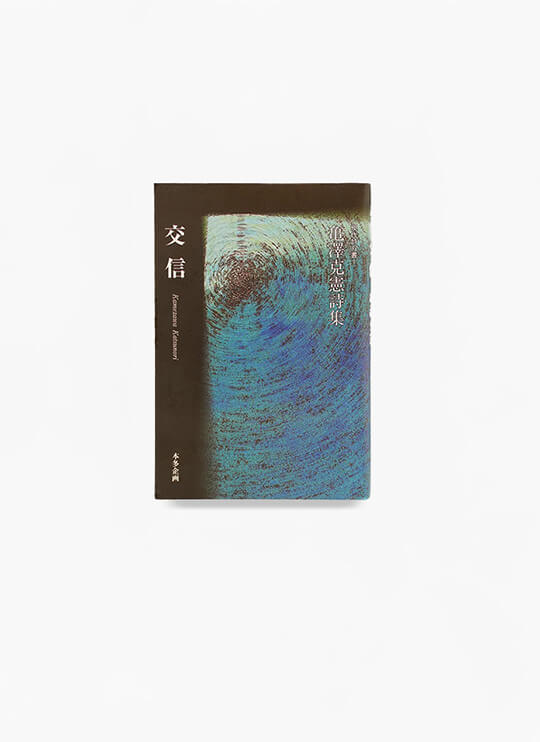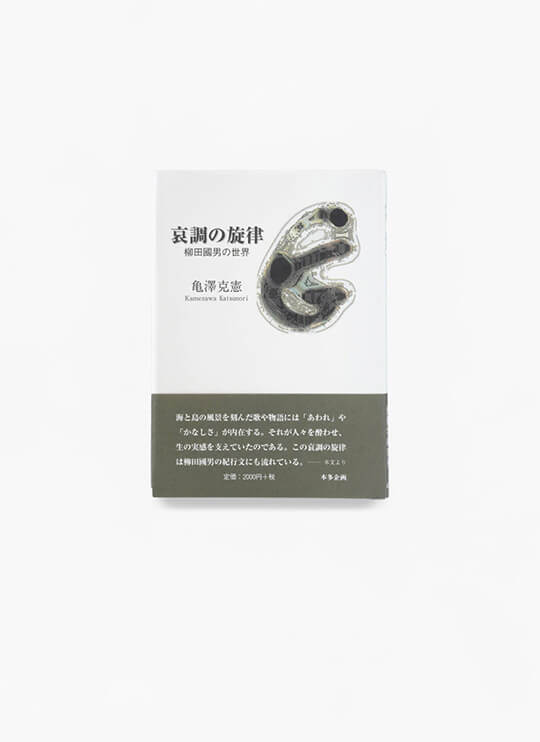青 島
青島には、淡島、歯朶(しだ)の浮島、鴨就(かもつく)島という呼び名がある。いずれも古い伝承の痕跡を残している。そこに古代海人族の霊魂観が読み取れる。青島は、本来は死者の島だったのかもしれない。元宮からは割れた弥生式土器が多数出土している。天の平瓮(ひらか)神事として磐(いわ)堺(さか)に素焼の皿や真貝を投げ入れ、開運厄払を占ったとされる。割れた皿や貝は死者の形代(かたしろ)ではなかったか。壊された土偶同様に、死体から豊穣をもたらす祈願神事でもあった。割ることで現世から来世へと送り出したのである。その通路を青の世界と命名し、青島がつくられていった。